車の操作方法・・・・走り出す前に!
-

マイカー装着用「補助ブレーキ」
「最終的にマイカーでの教習もしたいけど、マイカーでの教習だと、補助ブレーキが無いので、不安・・」と思われるお客さまへは、マイカー装着用の補助ブレーキをご用意して…
-

梅雨の時期や冬場に必須です・・・ガラス内側の曇り取り
ガラス内側の曇り取り方法 地味な項目ですが、雨の日や寒い日は、頻繁に窓ガラスが曇り、急に視界が悪くなったりします。 そのような時、慌てないように、曇り取りの操作…
-

走行前に、再確認!・・・「ハザードランプ」
画像にあるボタンが、ハザードを点灯させる為のボタンです。国産車・輸入車、すべての車で、共通の表示がしてあります。 ハザードボタンを押すと、車の四隅にあるランプ(…
-

雨天時でも慌てない・・・「ワイパー」の動かし方
国産車の場合、ハンドルの左にあるレバーを使用します。レバーを下に移動させるほど、ワイパーが動きが早くなります。 通常は、停止→間欠→連続(遅い)→連続(早い)と…
-

手元を見なくても操作できるように!・・・ライト類の操作方法
国産車の場合は、ハンドルの右側のレバー(ウインカーと同じレバー)を使用します。 輸入車の場合は、ハンドルの左のレバー、または回転式のスイッチを使用することが多い…
-

ウインカーの出し方
ウインカーを出す場合、国産車の場合は、ハンドルの右にあるレバーを使用します。輸入車の場合は、たいていハンドルの左にレバーがあります。 国産車から輸入車に乗り換え…
-
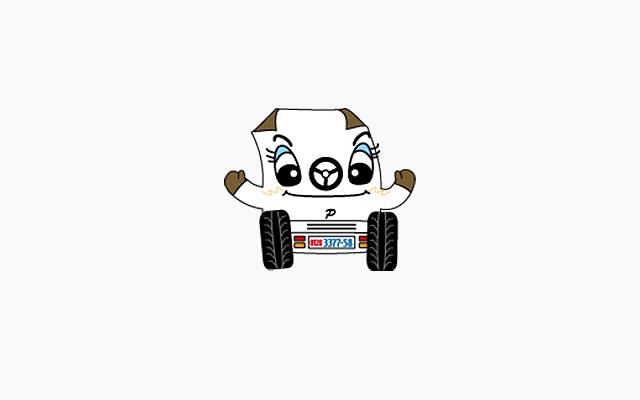
ハンドルを持つ位置とハンドルの握り方
ドライバーのレベルや走行状況で、ハンドルを持つ位置は変わります。 ペーパードライバーさんの初期段階の練習でのハンドルの持つ位置は、教習所で習ったように、「10時…
-

ミラーの合わせ方
ルームミラーの調整は、手動で合わせます。運転する姿勢でミラーを見ながら、左手で調整を行ってください。 写真のように、リヤウインドの中央が、ルームミラーの中央に写…
-

シートの適正な合わせ方
まずは、お尻をシートの背もたれに沿わせるように落とし込み、シートの奥深くに座るようにします。 ミニバンなど、座面の高さを調整機能の付いたシートの場合は、座面の高…
-

パーキングブレーキの解除方法
パーキングブレーキの解除で最も重要なことは、「解除し忘れない事」と「完全に解除する事」の2点。 パーキングブレーキは、車両を停めておく為だけの非常に弱いブレーキ…
